マイクラでおしゃれな建物を作る方法のひとつに、実在の建物をモデルにするやり方があります。完全に再現するのもいいですし、雰囲気だけを参考にするのもアリですね。ただ、マイクラでリアルな建物を再現しようとする時、意外と悩むのが「縮尺(スケール)」ではないでしょうか。
これを決めずに何となく建築を始めてしまうと、
- 思ったより中が狭くて装置が入らない
- 2階部分がやけに小さくなってしまう
- 全体がのっぺりしてしまう
…といった問題が起きやすくなります。たまによくあります。
そこで今回は、擬洋風建築の最高峰とも言われる「山形市郷土館(旧済生館本館)」をモデルに、マイクラ建築での縮尺の決め方について考えてみたいと思います。
普段はパソコンで設計することが多いのですが、今回はあえてスマホをつかってできるだけ簡単にやってみたいと思います。

こちらが、山形市郷土館です。「旧済生館本館」は、1873年に建てられた病院建築で、当時の最新技術と日本の伝統的な木造技術を組み合わせた“擬洋風建築”の代表的作品です。現在は「山形市郷土館」として一般公開されており、その八角形の中央塔やバルコニーなど、西洋建築風の装飾がとても印象的です。
実際にこの建物を見に行ったことがあり、いつかマイクラで再現してみたいと思っていた建築物の一つです。この写真も以前自分で撮ったものですが、残念ながら資料としては非常に少ないので、今回はweb上の写真も参考に建築しました。
明治時代初期、日本の大工たちが洋風建築を見よう見まねで取り入れて作った建物のこと。和風の技術に洋風デザインをミックスした独特の様式が特徴です。
今でも全国各地に保存されていて、見学できる場所もあります。マイクラでは木造で装飾の多い建物が再現しやすく、私もよく建築の参考にしています。

マイクラ建築において縮尺はどうして大事?
マイクラでは1ブロックの1辺が1メートルということになっています。プレイヤーは1.8ブロックですが、ほぼ2ブロックなのでほぼ2mですね(笑)この1mを当てにして作ってもいいのですが、ドアの大きさやプレイヤーの身長の関係で少し窮屈になってしまいがちです。
実際の建物には、「窓と壁のバランス」や「柱と天井の高さ」など、独特のプロポーションがあります。
こうした比率をマイクラで再現するには、ただ1m=1ブロックで置き換えるだけでは難しい場合が多いです。特に現実の建物をモデルにする場合、「どの要素をどれだけデフォルメするか」を考えてから始めないと、行き当たりばったりな作業になってしまいがちです。
縮尺を決めるきっかけになるもの
例えば、モデルにしたいと思った建物の窓が気に入ったなら、まずは窓だけ作ってみます。そうすると窓の大きさが決まるので、窓を基準に全体の縮尺が決まっていきます。この時、トラップドアや板ガラス1枚の大きさなどの「マイクラの世界の基準」にとらわれずに、自分が気に入って表現したいと思った部分に合わせて柔軟にデザインしてみるといいかもしれません。
他に、マイクラで基準になりそうなのは、中に作る設備の大きさ、周りの建物とのバランス感、ドアなどの出入り口のサイズ感、柱の太さ、階段の段数などでしょうか。マイクラだとドアや柵のサイズが決まっているので、その辺との兼ね合いで決めてもいいですね。
今回は、中央下から3段目のバルコニーの部分が一番横幅が小さいので、この窓のデザインを基準にして全体をスケーリングしていきたいと思います。



マイクラではドアはどうしても2ブロックの高さなので、マイクラのドアをそのまま生かしたければドアが基準になる。
トラップドアでデザインを補完したり、ドアを何枚も組み合わせて大きなドアを表現しても良い。
画像に線を引いて、縮尺を“見える化”してみる
基準にするパーツを決めたら、試しに作ってみたパーツと画像を見比べて、全体をグリッドに落とし込んでいきます。pcが使えればエクセルやnumbersを使って、画像の上に方眼を重ねるようにすると間違いないですし楽です。
なんですが、マイクラで現実の建物を完全に同じ縮尺、割合で再現することは難しいです。マイクラは基本的に立方体でできているので、どうしても現実の建物の装飾をデフォルメしたり、少し大きく作ったり、時には一部調整したりする必要がありますよね。
今回はスマホで参考図を用意するという試みでもあるので、iPhoneの写真アプリに搭載された機能を使って、スケーリングのイメージを作ってみることにしました。使ったのは描画機能に含まれている「定規」と「直線」です。

マイクラで再現可能にするため、完全な等間隔ではなくて「ここの幅を◯ブロックにする」「この柱の直線上に3階バルコニーのこの枠線がぶつかる」といった感じで、基準となる線を決めて区切っていくイメージで作ってみました。定規を当てて、だいたい1ブロック分が5mm程度のサイズになるように画像を拡大して区切っています。
直線を起きながら、「ここは銅かアカシアの階段かな」と使用するブロックもだいたい決めていきます。
正面の参考図が作成できたら、別角度から見た写真も並べて、スケール感を確認していきます。
↓Numbersで画像にグリッドを重ねる方法はこの記事の中で紹介しています。↓
ブロックの色と素材を決めよう
スケール感のイメージがだいたい固まったら、質感や色を見ながら使用するブロックを決めていきます。この時、使用する数も概算してしまうと素材集めが楽ですね。
元の建物に忠実に再現してもいいし、思いきって自分好みにアレンジしても楽しいですよね。色違いで何棟か並べてみるのもアリです。今回の「旧済生館本館」は明治時代の擬洋風建築ですが、もしこれが本格的な西洋建築だったら? そんなふうに想像してみると、ブロックの選び方や色使いもまた違ってきそうですよね。
ブロックの色合わせにはぜひともこちらの記事をご活用ください↓
建築する
あらかじめスケール感を計算して、素材の数を概算し十分な素材を用意してから建築を始めたのですが、構造が難しくかなり時間がかかってしまいました。窓や階段など、まだまだ作業は残っているのですが、とりあえず写真と同じアングルで並べてみました。本当は3階の窓より2階の窓の幅が狭いなど、細かい部分を手直ししたかったりはしますが……。ブログがいつまでも完成しないので一旦よしとします。
こちらは私が三階の窓に着目して再現した「旧済生館本館」ですが、どれぐらいディティールに拘りたいかや、建物の用途によって様々な異なるスケール感での再現が考えられるでしょう。



1階部分です。14角形の本体の正面部分に、8角形の棟がくっついています。かなり独特な形。マイクラでは表現できる角度にかなり制約があり難しいですね。
中庭は庭園になっています。枯山水をマイクラで表現するのもまた難しかった。

塔の部分の2階は本来は16角形になっているようなのですが、円形に近いかたちでどうにかしました。マイクラでは直線の角度を細かく調節できないので、小規模な多角形は難しいですね。
建て始めは、最初に試作した3階バルコニーを基準にして1階正面の幅を決め、同じ長さで8角形ができるように正面の塔のサイズを決めました。次に、正面から見た時に見えている範囲をイメージして後方の14角形を作りました。今回の建物は多角形や円を多用した複雑な構造ですが、「1辺の長さを割り出して形を作っていく」のはどんな建物でも同じですね。
別の縮尺でも作ってみました
扉をマイクラのサイズに合わせたバージョンも作ってみました。かなり小さい建築になるので、どうしても窓のディティールなどは思い切ってデフォルメしないといけなくなります。個人的にはマイクラの建物は小さい&狭い方が好きなので、こっちもありですね。ただし、小さい方はバルコニーに出られません……。
ドアをマイクラサイズにしたバージョン


3階の窓のディティールにこだわってそれを基準にしたバージョン


実物


実はこの建築はまだ作業途中なので、完成したら別記事で建築の振り返りをしたいと思っています。小さい方の建築も、その時に一緒に紹介できたらと思っています。
縮尺を決めてから建てると格段に楽!
今回は、マイクラで建築をする時の「縮尺」について整理しました。特にモデルにする建物があるときには、一番表現したい部分や窓の大きさを基準にして縮尺を決めてから建てると良いです。「1階からなんとなく作り出したら、2階が小さくなって窓が作れない」とか、「屋根を奇数にしたかったのに偶数になった」などのトラブルが減るのでおすすめです!

とは言いつつ、ろくに設計をせずに建て始めることもよくあります。満足のいく建築ができればそれでも良いのです。


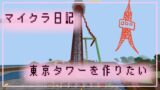


コメント